| 佐村河内騒動に思う | Quartet Berlin-Tokyo |
| 佐村河内騒動に思う | 2014.02.20 | |
|---|---|---|
|
例の代作・全聾疑惑問題。 オリンピックの話題と一通り証言が出揃ったこととで一旦鎮静化していますが、全聾疑惑の解明はこれからです。 彼のCDを2枚買い気に入って聴いている私としては、複雑な思いでいっぱいです。 遅ればせながら、この件について思うところを記録に残しておくことにしました。 [2014.2.22]「絶対音感に対する過剰な期待」の項を追記しました。 楽曲について
この騒動で一年ぶりにCDを引っ張り出してきて聴き直しています。 私は「交響曲第1番」「弦楽のためのソナチネ」「弦楽四重奏曲第2番」が気に入っています。 プロによると佐村河内氏の曲はどれも「後期ロマン派風の楽曲」で「現代音楽を勉強した作曲家なら誰でも書ける曲」なんだそうです。 でも、現代の作曲家はロマン派風の音楽を新しく作ってはくれません。 代作であるがゆえに、注文による作曲であるがゆえに生まれることのできた楽曲です。 曲を気に入っている私としては、結果オーライです。 交響曲第1番はチャイコとマーラーとショスタコがてんこ盛り、らしいですが、そんなの関係ない。 だって、耳に心地よい音楽なんだもの。 音楽って、音を楽しむ、と書くじゃないですか。 少なくとも私はこれらの曲を楽しんで聴いています。 新垣氏の著作権放棄について
代作者の新垣氏は業界では著名な現代音楽作曲家であり、ピアニストでもあるとのこと。 当初、新垣氏が会見で著作権を放棄すると言われたのは罪の意識によるものかと思っていましたが、そうではなさそうです。 代作で書いた楽曲は新垣氏の「創作」とは新垣氏自身が思っていないために著作権を放棄するんだと私は理解し、納得しています。 現代音楽の作曲家は、過去の技法でも作曲できるけど、先人の手垢のついた古い作曲技法ではなく現代の作曲技法で作曲したいんだそうですね。 代作で作曲した曲は新垣氏が真面目に書いた曲ではあるけれど、それは過去の作曲技法を組合わせて作業をしただけであり、心血注いで創作した作品とは異なる、と伊東乾氏が日経ビジネスプレスに書かれていました(後述あり)。 伊東氏は入試問題の作成に例えてその思いを説明してくれており、わかりやすかったです。 現代音楽について
先日、弦楽カルテットのコンサートで美しい演奏を聴いた際に「この世には美しい曲がごまんとある。それらを乗り越えて後世に残る曲を書くには先人と同じことをしていてはいけないんだ」と強く感じました。 とはいえ、残念ながら私は現代音楽に疎く、聴くのも弱いんです。 現代音楽を耳にするチャンスも少ないから、余計に遠ざかっています。 今回、新垣氏という現代音楽作曲家の名前を知ったのでYoutubeで彼の作品を聴いてみましたが、聴いていて心地よくないので途中で聴くのを止めてしまいました。 過去の名曲を越えるには新しい試みが必要という理屈はわかるけど、それが耳に心地よくないものである必要がどこにあるの? 現代音楽がもっと聴きやすいものにならないのは何故なんでしょうね? 現代音楽というジャンルはまだ試行錯誤中なのでしょうか? 代作について
作曲業界では代作が当たり前に行われていることらしく、需要と供給あってのことなので、代作自体は特に問題視することではないと思ってます。 だけど、それを全聾の作曲家が書いたことにするのはルール違反です。 それに、そもそもは代作としての依頼ではなかったそうです。 テープに録音された断片素材を提示され「オーケストラ用の楽曲として仕上げてほしい」という依頼が佐村河内氏からの最初の仕事だったとのこと。 でもそれが後になって「佐村河内の名前で発表する」と言われてしまった。 それを承諾したのは新垣氏の若さのためもあるでしょう。 43歳の新垣氏が18年間代作を続けていたということは、最初の仕事は25歳の時です。 大学を卒業したばかりの頃です。 それがまさか代作という形で18年も続くことになろうとは、当時は夢にも思わなかったに違いありません。 新垣氏の辞表提出について
新垣氏は一連の騒動のけじめとして大学を退職する決意が強いようですが、けじめをつけるべきなのは佐村河内氏であって、新垣氏ではありません。 この騒動で学生たちが新垣氏から学べなくなるとしたら、残念でなりません。 佐村河内氏は嘘をついていた世間に対してもですが、まず新垣氏に対して謝罪すべきではないでしょうか。 全聾疑惑
SMAP稲垣くんが後ろから話しかけた言葉に答えたシーンの動画を見ました。 これは明らかに聞こえています。 稲垣くんの声は注意を引くような音量ではなく、普通の会話レベルよりも抑えた音量でした。 これが聞き取れるなら、6級の「一側耳の聴力レベルが90dB以上、他耳の聴力レベルが50dB以上のもの」でさえ相当しないでしょう。 私は片耳が70dB以上の難聴持ちですが、50dB程度の頃でも悪い耳の側から話しかけられると聞き取れませんでした。 姿が見えていても聞き取れないんです。 周囲に撮影スタッフや手話通訳者がいる状況で、見えない相手の発言が自分への問いかけと理解して答えることができたということは、言葉の意味を理解できる程度に聞き取れていたということ。 少なくとも、片耳はほぼ正常に聞こえているんじゃないでしょうか。 聴力の程度は本人にしかわからないことであり、障害者手帳の支給は性善説を取らざるを得ません。 それを悪用する人がいるということは本当に悲しいことです。 大音響の耳鳴りや頭鳴りも嘘なのでしょうか。 そういった症状に苦しんでおられる聴力障害者は多数おられるでしょう。 障害に苦しんでおられる方々への冒涜だと思います。 全聾をアピールした売り方について
クラシックで売り出そうと思ったら、まずは聴いてもらわなくてはなりません。 そのためには過剰なくらい目立つキャッチコピーが必要です。 コンクール優勝歴、容姿、障害、など人と違って目立つ部分があれば、販売戦略上有利です。 私もそういうコピーで知った奏者のCDを何枚か持っています。 ですから、メディアに注目してもらうために佐村河内氏が人一倍キャッチーなコピーをつけたのは戦略として正しいと思います。 でも、「全聾」「作曲家」のどちらもが嘘だったとは! 失望を通り越して、呆れてしまいます。 被爆二世が書いた「HIROSHIMA」
私が佐村河内氏に一番興味を持ったのが「被爆二世が書いたHIROSHIMA」という部分です。 被爆二世であり、その影響かもしれない障害を持ったことで、ヒロシマに対する思い入れはさぞかし重く深いものがあるのだろうと。 実際、私がこの曲を聴いて感動したのは、「HIROSHIMA」という曲だからという部分が少なからずありました。 なので、ヒロシマを思って書かれたのではない曲に「HIROSHIMA」と銘打って売り出したことには憤りを感じます これからはこの曲のことは原題の「現代典礼」と呼ぶことにします。 メディアについて
報道によると、稲垣くんとのやりとり以外にも、取材をしていく中で全聾に疑問を持つ出来事が複数あったようです。 その際に疑問を明らかにし、真実を追求することはできなかったのでしょうか。 視聴率を上げるためには疑問をスルーすることが必要だったのでしょうか。 メディアの報道は、まず疑ってかからなくてはいけないのでしょうか。 偽ベートーベンに日本中が騙されたことは余りにも滑稽です。 (専門家の多くは騙されなかったようですが) 絶対音感に対する過剰な期待[2014.2.22追記]
私を含め、大勢が騙された一因に絶対音感に対する過剰な期待があると思います。 以前、「絶対音感」という本がベストセラーになりましたね。 あの本が、絶対音感を持つ人への憧れと距離感を育てたと思います。 凡人からすると想像もつかないような能力を持った天才なんだ、という距離感です。 オーケストラ曲を作曲するためには絶対音感よりも作曲技法だったり様々な楽器の音色や特性の知識だったり、様々な知識と訓練が必要でしょう。 それらを全てひっくるめた能力に対し、絶対音感の一言で過剰に期待、というか、夢を見てしまったんです。 「そんな超人的なことが現実に可能なのか?」という疑問に対して「だって天才だもん」の一言で済ませてしまうほどに。 ベートーベンという前例があることが、盲信を後押ししました。 ベートーベンに出来たんだから、現代の作曲家にも出来るはずだと。 でも、ベートーベンは失聴するまでに多数の経験があったから、聴力を失った後でも作曲ができたんですね。 指揮者をされている先輩が「オーケストレーションは何度か曲を書いて訓練しなければ出来ない」と言われていました。 けれど、一般大衆にはそんな専門的なことはわかりません。 新たな「天才」が現れたら、また飛びついちゃうかもしれません。 最後に
この騒動に関する記事は複数読みましたが、前述の伊東乾氏の記事が一番納得がいったので、参考情報としてリンクを張っておきます。
久々に長文を書きました。一日で書いたわけではなく数日かけて少しづつ書き溜めたものです。言い足りない箇所もありますが、もう書き足す根性が無い〜(^^; 最後まで読んで下さった方、ありがとうございました。 | ||
| Quartet Berlin-Tokyo | 2014.02.15 |
|---|---|
|
Quartet Berlin-Tokyoという弦楽四重奏団の演奏会に行って来ました。 弦楽カルテットの生演奏を聴いたのはすごく久しぶりです。 生演奏はやっぱりイイ! 音が体に沁み渡るようでした。 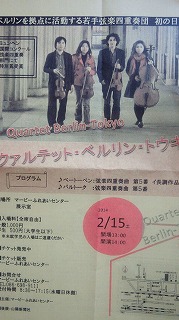 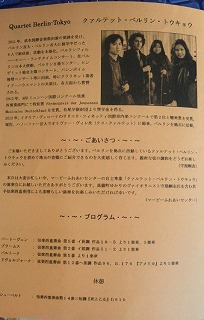 Quartet Berlin-Tokyoはベルリンを拠点に活動する若手カルテット。 1stVn奏者が地元出身です。 ホールの自主事業での演奏会とのことで、入場料1000円と格安のコンサートでした。 格安なかわり、音楽ホールではなく展示室を使っての演奏会。 気軽にクラシックを聴いてもらうにはいい企画ですね。 実際、楽章の度に拍手する人が少なからずいました。 顔なじみのアマオケ奏者も多数来られてました。 開場に着いたのが早かったので、チェロ側最前列席をゲットできました。 小さな会場なので、チェロとの距離が2m、1stVnとの距離が4m、くらいの至近距離です! チェロの音がバンバン響いてきて凄かったです。 奏者がお互いに確認し合いながら演奏するところもよく見えました。 一番長身な2ndVnが体をちんまりと丸めて演奏している姿が可愛かったです♪ 以下、プログラムです。
どれも聴き応えのある演奏でした。 奏者は皆若く、意欲的な演奏。 特にチェロ奏者のダイナミックな演奏が目立っていました。 死と乙女の2楽章の盛り上がる箇所でチェロのアップボウがA線に引っ掛かって弓を動かせなくなりチェロの音が途切れる、というハプニングがありハラハラしましたが、その直後のチェロのカッコいいメロディ(大好きな箇所です!)には間に合って一安心。 前半の、美味しいところを楽章単位でというプログラム構成は、ベートーベン→ブラームス→バルトークと時代が進む度に音楽が進化していく様子がよくわかって面白かったです。 先人の偉大な名曲の数々を越える作品を生み出すには先人と同じことをやっていてはいけない、という現代音楽の縛りがわかったような気持ちになりました。 今日の感想。 世の中には美しい音楽がごまんとあるんだなぁ。 もっともっと沢山、美しい音楽を生で聴きたいなぁ。 音楽が趣味と言っても弾く方がメインな私ですが、美しい音楽を聴く喜びは何物にも換え難いですね。 | |